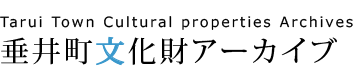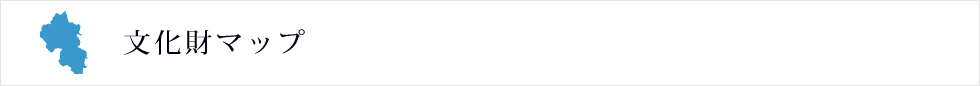
- 垂井町文化財アーカイブ
- > 文化財マップ
- > 検索結果
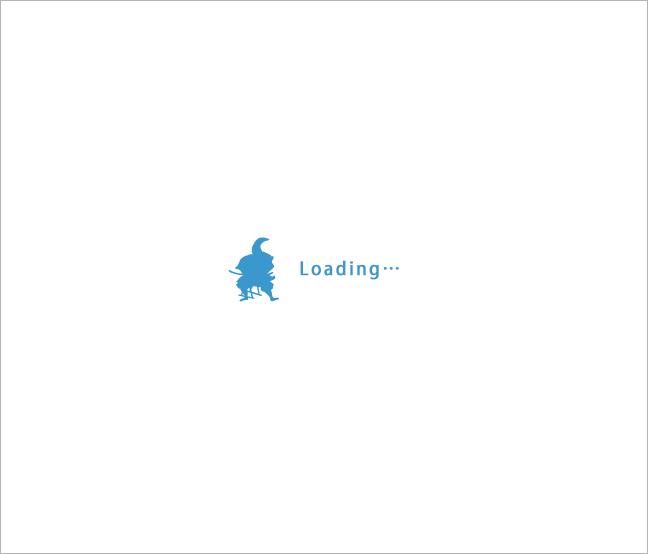
垂井町文化財マップは、垂井町内に所在する国・県・町指定文化財、国登録文化財を紹介するものです。
左の検索ナビゲーションより、「種別」「キーワード」にて検索いただけます。
また、タブ切替により「マップ一覧」「リスト一覧」を切り替えてご覧いただくことができます。
当一覧を利用し、垂井町の文化財に多くの方が触れていただけたらと思います。